施設概要FACILITIES
SHOWAグループ総合体育館
フロアマップ
1F
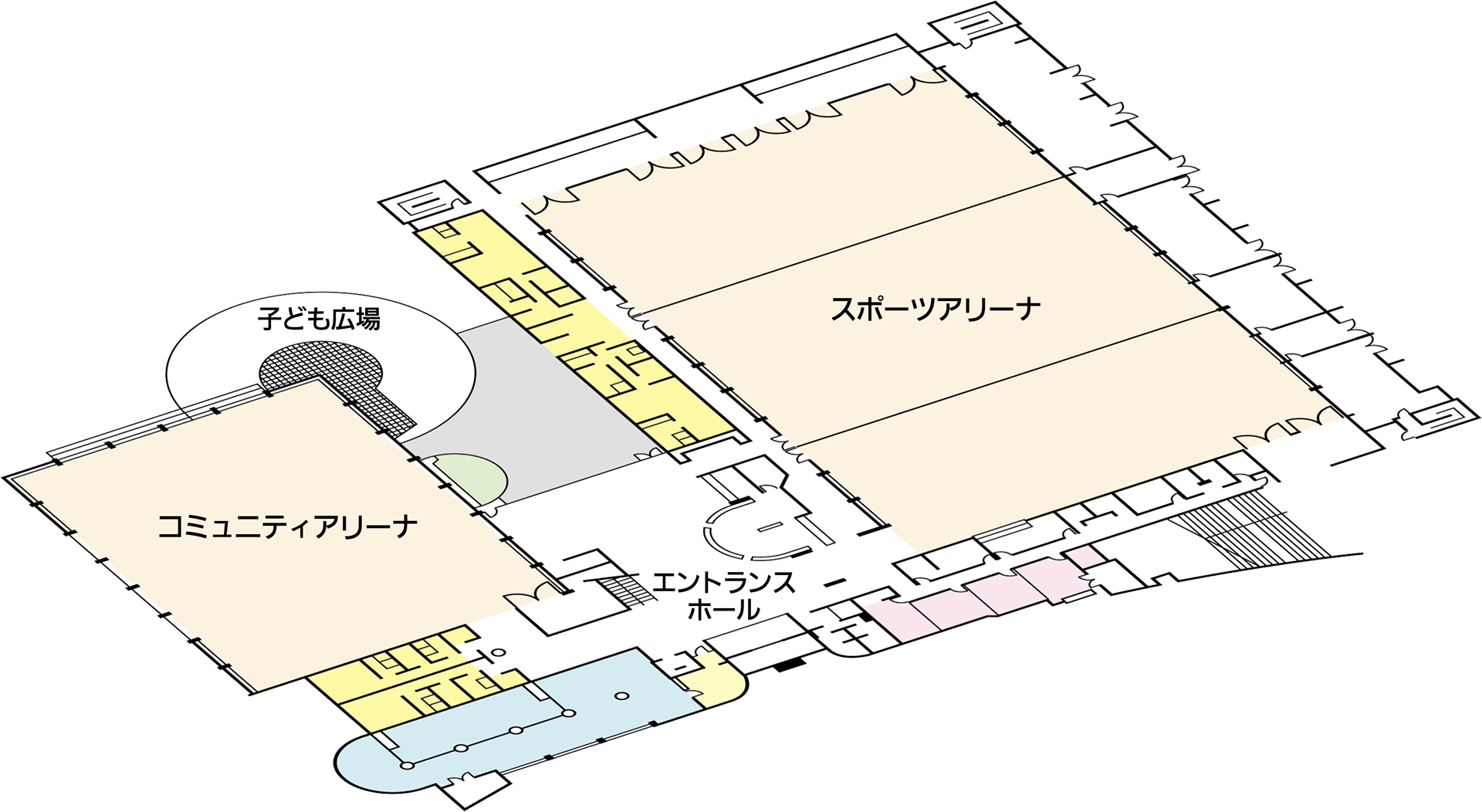
2F
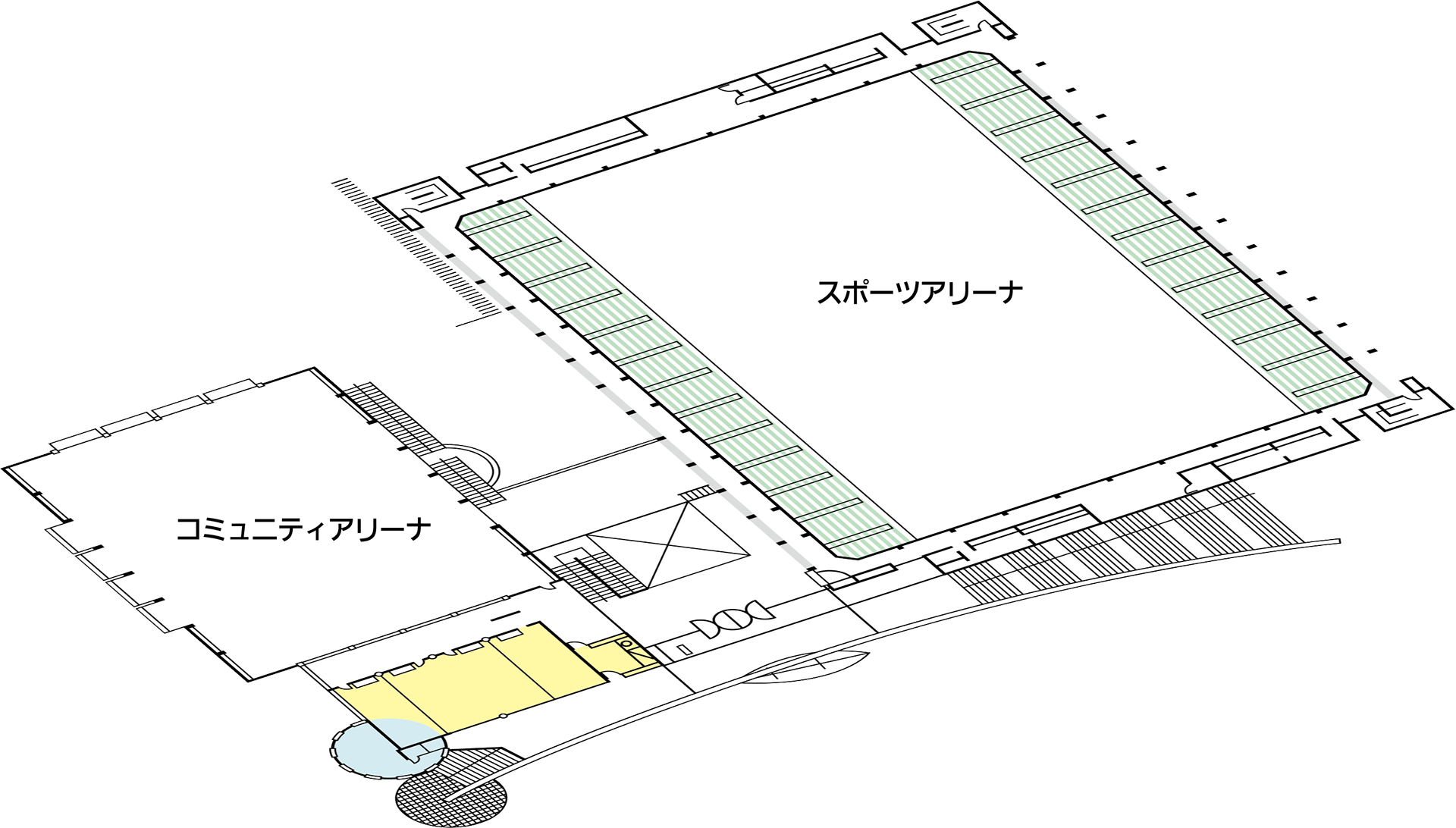
施設紹介

スポーツアリーナ(メインアリーナ)
様々な競技に対応でき、国際試合が開催できる本格的なアリーナです。
観客席からは迫力あるプレーを観戦することができます。
【対応競技】
- バレーボール(3面)
- バスケットボール(3面)
- バドミントン(12面)
- ハンドボール(1面)
- テニス(3面)
- フットサル(1面)
- 卓球(20面) 等
【仕様】
幅 65m / 奥行 40m (2,600m²)
天井有効高さ 13.5m
観覧席(固定席) 1,800席
国際試合に対応
※移動観客席86人掛け×8台 有

コミュニティアリーナ(サブアリーナ)
バスケットボールやバレーボールなど、サークルや個人で気軽に使用できるアリーナです。
【対応競技】
- バレーボール(1面)
- バスケットボール(1面)
- バドミントン(6面)
- 卓球(12面) 等
【仕様】
幅 40m / 奥行 30m (1,200m²)
天井有効高さ 13.5m
- 練習用としてはバレーボール・バスケットボール2面可
- 2階ギャラリーからコミュニティアリーナを見渡すことができます。

ランニングコース
スポーツアリーナ2階に1周250mのランニングコースがあり、どなたでも気軽に走ったり、ウォーキングすることができます。
(大会時など使用不可)

研修室
講習会や会議、ヨガ、ピラティス、ダンスなどの練習に使用することができます。
【仕様】
220m²(11m×20m)
最大120名収容
- 可動間仕切りで3室に分割することができます。
- 分割使用の場合はA 30人 B 42人 C 24人となります。

トレーニングルーム

フィットネススタジオ

市民クラブルーム
市民の方が会議や打ち合わせ、勉強会、懇親会などに使用することができます。
【仕様】
延床面積 59m²(トイレ/ミニキッチン付き)
テーブル、イス、応接セット、ホワイトボード、冷蔵庫
使用案内
スポーツアリーナ・コミュニティアリーナ
- 開場時間
- 9:00~21:00 ※受付終了20:30
- 休館日
- 第3水曜日(第3水曜日が祝日の場合は翌日)
年末年始(12月31日~1月1日まで)
年2回機械点検日を設けます。 - 使用方法
- アリーナを使用される方は加古川市スポーツ施設予約システムへの登録が必要です。
使用者登録を行うと、インターネット、携帯電話から予約をすることができます。 - 予約システム登録方法
- 総合体育館のフロントで受付しています。必ず身分証(ご本人が確認できる物)をご持参ください。ご本人以外の登録はできません。
- 予約方法
- 総合体育館受付窓口、インターネット、携帯電話、市内の公共施設に設置してある端末機から予約ができます。電話での予約受付はできません。
毎月20日~月末に4か月先の1か月分の抽選予約を受付することができます。
翌月1日に抽選を行い2日に結果が出ますので、お客様ご自身で抽選結果をご確認ください。
3日以降は空きがあれば即時予約可能です。
- 附属設備(器具、備品)は数に限りがありますので、予約と同時に使用される備品も申込するようお願いいたします。
- 附属設備の使用は先着順です。申し込みが遅れた場合、ご希望に添えない場合がございますのでご注意ください。
市民クラブルーム
受付方法
- 市民クラブルームのご使用はフロントにて所定の用紙をご記入の上、お申し出ください。
(電話でのご予約はお受けできません。) - ご使用の受付は使用希望日の2週間前からとさせていただきます。
- ご使用前には使用に関するヒアリングを行わせていただきます。
確認事項
- 申込みは加古川市民の方とさせていただきます。
- ご使用は8名以上でお願いいたします。(最大15名まで)
- 以下の目的でのご使用はできません。
- 営利を目的とする使用
(企業の会議・販売・講習会・講演会など) - 教室・習い事の場としての使用
(講師料・謝礼金の授受の有無にかかわらず、同曜日・同時間帯での連続のご使用は教室と解釈されます。) - 政治活動、宗教活動に関する使用
- 公序良俗に反する使用
- その他、施設側がふさわしくないと認めた場合
- 営利を目的とする使用
その他
- ご使用前、ご使用後は体育館フロントまでお越しください。
- ご使用中、施設職員が巡回確認を行う場合があります。
- 施設使用後は備品を元の位置に戻し、清掃を行なってください。
- 施設、備品などを破損された場合は速やかにお申し出ください。
PFIとは?
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う方法です。
民間事業者の経営ノウハウや技術的能力を活用でき、事業の全体管理が効率的に行えるため、コスト削減、質の高いサービスの提供が実現できます。従来公共団体等が行ってきた事業を民間事業者が行うため、官民の適切なパートナーシップが形成されます。